いやはや。ついにこの日が来てしまいました。
Amazonの電子書籍「Kindle」やAppleの電子書籍「ブック」で、簡単に本が出せるようになったというのは知ってはいたものの、自分が経験した中で本にしやすい「旅行記」は、旅行記として皆さんに購入してまで読んでもらえるような旅行は結婚以降なかなか行くことができず、長年「いつか出してみたいな〜」と思うぐらいで止まっていました。
そんな中で突然のご報告ですが、ついに人生初出版を経験することができました。
出版した書籍のタイトルは……
『規程チャットボット 実践ガイド:構造化データ(JSON)× 高精度プロンプトで誤答を防ぐ』
という、まさに自分の仕事と趣味(?)のど真ん中に突き刺さるテーマです。
出版日は2025年7月。完全に個人出版、いわゆるKDP(Kindle Direct Publishing)を利用してのリリースです。
目次
そもそも、最初は当ブログとは別に「note」を作ろうと思ったところから
いきなり出版の告知でしたが、そもそもこのブログをやってはいたものの、たまにパソコン関係のネタは入っているものの、基本的に自分が気になった製品の紹介だったり(なので、いままでレビューしてた会社から新製品が出ても載せないことも多い)、買ったもののレビューや、食べたものや旅行記といった内容がメインなので、自分としてはPC関係の話は少し浮いていると感じていました。
そんな中、自分も参考で読むブログ的なメディアとしての「note」に魅力も感じていた(気軽な「いいね」とか「フォロー」とか)ため、ここでAI関係を中心としたブログをnoteで展開しようと思ったのです。
その名も「ぷくおのAIラボ」という可愛い名前なのですが、ここでChatGPTの便利な使い方を書いていこうと始めたのでした。
noteに数個記事を書いたあと、次に書こうと思ったのが「PDFファイルを読み込むより正確な回答を出すための構造化されたJSONファイルを作る」という内容。
なぜ出版しようと思ったのか?
現在、仕事でもプライベートでもChatGPTやGeminiといった生成AI、さらに検索に特化したPerplexityなど、AIの力を存分に使っていますが、そんな中で特に力を入れることになったのが、仕事で「規程(条文・別表・様式を含む」をしっかりと読み解いて、質問に答えてくれるというAI。
最近、RAGという言葉を目にした方もいると思いますが、AI自体のトレーニングには専門的な知識と膨大な計算リソースが必要となり、大手企業のプロジェクトでもない限りなかなか実行に移すのは難しいなか、既存のAIに特定のデータを読ませることで、そのデータに含まれていた内容を答えてくれるというのがRAGの基本的な考え方。
有名どころとしてはGoogleのNotebookLMという情報整理・リサーチアシスタントツールがありますし、有名なChatGPTやGoogleのGeminiといったAIでも「知識」としてデータを入れて、単にチャット内で回答させたり、データを入れたうえにどのように答えさせるかをあらかじめ指示したうえで単に質問だけすれば回答してくれる「カスタムAIボット」というのもあります。
このカスタムAIボット、ChatGPTでは「GPTs」という機能があって、自分専用だけだったり、組織内で共有、ChatGPT全ユーザー向けに公開といった様々な公開レベルが設定できるので、ここで会社の規程に応えてくれるボットがあれば便利じゃない?と思ったのがそもそもの沼の始まり。
最初はPDFを読み込ませるだけでチャットボットを作ってみたのですが、思ったように回答してくれない…。
そこで「構造化データ×プロンプト設計」のアプローチにたどり着き、試行錯誤を繰り返すことに。
気づけば、自分でも驚くほど深くこの分野にのめり込んでいました。
ChatGPTに聞いて、GPTsの挙動を正しくしていく道のり
先程、PDFを読み込ませたけど思ったように回答してくれない。と書きましたが、ChatGPTに原因を聞いていくと、AIはPDFデータを読み込むのが苦手とのこと。
もちろん、昔のOCRに比べたら雲泥の性能差があるわけですが、それでも第1章第1条第1項 〇〇〇〇というのが、人であれば前半は条項の番号に関する内容で、後段はその規程の中身というのが一目瞭然ですが、AIにとっては1つの文字列に過ぎません。
また、表(特にセル結合とか結合していなくても透明な線で結合っぽく処理されているセルとか)や様式など、さまざまなデータを読んで理解してもらうにはまだまだAIの性能が足りていません。
そのような中で、AIが理解しやすいように規程をJSON形式で構造化させてあげると良いということで、試しにいくつかの規程をJSON形式にしたところ、回答精度が雲泥の差となったのでした。
さらに、AIとしては文章のチャンク化(情報を小さな塊に分ける)とかベクトル化(単語同士の関係性・方向性を持たせた情報)に変換させ、AIに融合させるとさらに回答精度が良くなるそうなのですが(ちょっと端折ってます)、そこまでやってしまうと規程の改廃や新規規程策定時のメンテナンスが困難というデメリットも見えてきました。
このことから、全規程をJSON形式に変換し、これでいよいよ規程ボットの完成!
と思ったのですが、GPTの設定で「インターネット検索」をオフにしているのに、規程に書かれていない情報を回答に混ぜ込んできたりして、さらに沼に入ってしまいます。
この沼を解決し、さらにGPTモデルの選定を行った結果、あまり待ち時間がかからないのにかなり正確な回答ができるように!さらに、回答で不正確だったところもメンテナンスを行うことで正しい回答が出せるようになったのでした。
「これって今の世の中に結構必要とされているのでは?」、「これは…同じように“社内のルールや規程”を活かしたい人たちに役立つかも」
そう思ったので、改めて同様の本がないか調べてみることに。
KDP出版へ
Kindleストアを覗いてみても、IT関係のニュースやコラムを見てみても、それぞれの仕組みについて詳しい情報は載っていますが、実際にメンテナンスのことまで考えて構成されている資料は見当たらず。
なら自分の経験をブログだけじゃなく本に出してみよう!と思ったのがきっかけ。
初めての出版ということで、本の構成はどうしようとか、有料の本となる以上、内容に間違いはないかとか、相当悩みました。
構成については、IT関係の本の章の構成を見たり、ChatGPTに相談したりし、さらに内容についても実際に規程ボットを作った経験と、さらにその内容を再度検証して、とにかく5.5万文字の本が出来上がったのでした。
もうこれで出版!と思ってChatGPTに本のレビューをしてもらったところ、まさかの本の構成自体を組み替えた方が読みやすいというダメ出しをもらいます。。。
というのも、本を書いている中で分かりやすいように詳しく書き過ぎたり、追加で書いたパートなどがかなり多くなってしまって、最初に考えていた章のバランスが崩れてしまったのでした。
いっそ、書いた内容を組み替えするだけで出版しようかと思ったのですが、ChatGPTが出してきた改訂版の構成の方が確かに読みやすい(笑) そのため、最初の本のデータは幻の第1版として未公開にして、再度本の執筆に向かったのでした。
改めて本を執筆した結果、今度は10万文字近い量(原稿用紙250枚近い)になりましたが、かなり分かりやすい構成・内容になったと思ったので、本のタイトルを調整し、表紙を作り、そしてKDPのアカウント登録と内容の登録を済ませ、ついに出版へ向けた最後の申請ボタンをクリック!

▲ ついに出版登録をする瞬間
このブログのように、無料で書いている文には責任が無いわけではありませんが、それほど責任感はなく書き連ねていくことができるのに対し、本を出すとなると本当に間違いがないか心配で、ボタンをクリックするのがかなりのプレッシャーでした。
KDPは申請ボタンをクリックしてから、どのような作業が行われているのかは分かりませんが本のレビューが行われ、問題が無ければ72時間以内に公開となります。
今回の出版では丸2日程度で審査が終わり販売が開始されました。
本の特長

▲ 今回執筆した「規程チャットボット実践ガイド」表紙
この本は、特定の業界や職種をターゲットにしているわけではなく、
– AIを業務で活用したいけど、どう始めればいいかわからない
– 社内にある大量の「ルール」「規程」「様式」…どうにか活かせないか?
– ChatGPTをちゃんと使いこなせるようになりたい
といった方には、きっとヒントになるはず。もちろん、ChatGPTの知識ゼロでも読み進められるよう、用語解説や具体例も豊富に盛り込んでいます。
▼ 書籍はこちらから
📘 Kindleストアでチェックする
さいごに
最初は便利に使っている事例の紹介をしたい→けどこのブログだとちょっとなじまない→noteで書こう→重めのテーマを書こうと思ったら本になってしまった というまさかすぎるストーリーとなりました(笑)
引き続き、このブログとともに新たにはじめたnote。そして私と同じように組織の規程だったり決定事項などを正確にAIでチャットボットを作りたいけど困っているという方は、ぜひ『規程チャットボット 実践ガイド』も手に取っていただけたら嬉しいです!そしてレビューを書いていただけたらさらに嬉しいです!!
—
📚 本書:『規程チャットボット 実践ガイド』
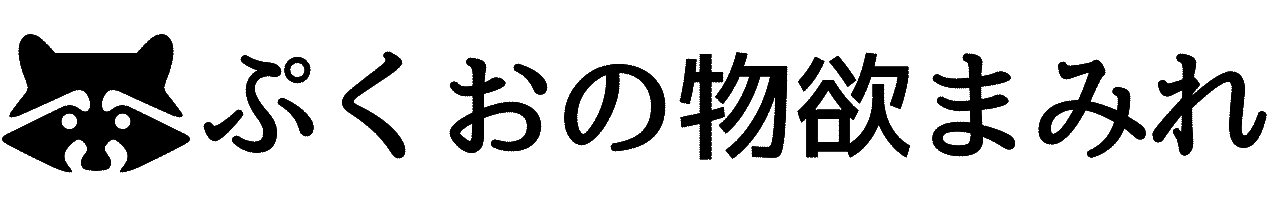













コメントを残す