2026年5月19日搭乗分から、ANAの国内線運賃が大きく変わります。これまでは一律だったように見えるサービスと価格の関係に、明確な“選択肢”が設けられるようになります。
一見、柔軟な制度に見えるこの改定ですが、サービスを選ぶ側にとっては「わかりづらさ」や「考える手間」を感じることも。さらに、国際線と共通化されることで、私たちが慣れ親しんだ国内線のルールにも見直しが入ります。
これは単なる料金の見直しにとどまらず、ANAが目指す「国内・国際の垣根を超えた一体型サービス化」の一環。その背景とポイントを、できるだけわかりやすく整理してみます。
目次
ついに日本のFSCも「料金はサービス連動型」に
これまで日本のフルサービスキャリア(FSC)は、基本的に「同じエコノミーなら同じサービス」という考え方が主流でした。しかし海外ではすでに、座席指定の有無や手荷物の量で価格が異なる「サービス分離型」の運賃体系が一般化しています。
今回ANAが導入する新運賃体系は、それを国内線にも適用するものです。
新しい3つの運賃タイプ

2026年5月19日搭乗分から、ANA国内線の運賃は以下の3種類に整理されます:
1. シンプル
最も価格を抑えた運賃
付帯サービスは最小限
搭乗前日まで購入可能
2. スタンダード
一般的なサービス(事前座席指定、アップグレードなど)を網羅
予約変更も可能(手数料あり)
搭乗前日まで購入可能
3. フレックス
予約変更に手数料不要
空席待ちや当日変更も可能
搭乗日当日まで購入可能
空席予測による変動価格制も導入され、混雑具合や予約のタイミングに応じて料金が変わります。つまり、早めに予約すればお得、混雑時や直前購入は高めになるというLCC的な仕組みが、ANA国内線にも本格導入されることになります。
その他の主な変更点
■ 往復運賃の新設
片道運賃に加えて、割安な往復運賃も導入。これまで別々に予約していた人にとっては、価格メリットがあります。
■ 乗り換え(経由)条件の緩和
24時間以内であれば、ANA指定の経由地で乗り継ぐ旅程も選びやすくなります。たとえば「札幌 → 福岡(羽田経由)」といった乗継が現実的な選択肢になるかもしれません。
■ アップグレード手段の拡充
これまでは有償・ポイントによるアップグレードが主でしたが、新たに「マイルによるアップグレード」も可能に。柔軟性が広がります。
特典航空券の進化
ANA国内線特典航空券では、乗り継ぎ旅程の選択肢が増加。
国際線の特典航空券では、片道旅程での利用が可能に(2025年6月24日発券分から)。
これにより、特典航空券の使い勝手がより高まります。出張や短期旅行のプランが立てやすくなるかもしれません。
国際線との共通ルール化で変わる点
ANAは、スペインAmadeus社の国際線旅客システムと自社の国内線システムを統合し、ルールも共通化します。これにより、予約やチェックインなどの手続きが国内線でも国際線と同様の仕様になっていきます。
代表的な変更点は以下の通りです:
名前表記の変更:カタカナ → ヘボン式ローマ字へ
幼児の定義が変更:2歳未満 → 1歳未満(2歳児は座席確保が必要に)
ANAジュニアパイロットサービスの対象年齢が5歳からに変更
インターネット空席待ちが非会員でも可能に
手荷物ルールが「重量ベース」→「個数ベース」に変更
株主優待の使用ルールも変更(有効期間が1年半に延長、購入時に優待番号登録が必要)
まとめ:私たちは“選ぶ側”に
今回の制度変更は、ANAにとっては「グローバルスタンダードへの対応」。一方、私たちユーザーにとっては、「何を重視するかを自分で考えて選ぶ」ことを求められる時代になった、ということかもしれません。
「時間に余裕があるから安く済ませたい」
「乗り換えの多い旅だから、変更可能なチケットにしたい」
「荷物が多いから、手荷物ルールを確認しておきたい」
──そんなふうに、自分の旅のスタイルを見直すきっかけになる変化です。
正直に言えば、ここまで細かく分類されると「だったらLCCでもいいかも…」という気持ちも浮かびます。でも、きちんと比べれば見えてくる快適さや利便性もあるはず。旅において「何を重視するか」を再確認する、ちょっとした分岐点なのかもしれませんね。
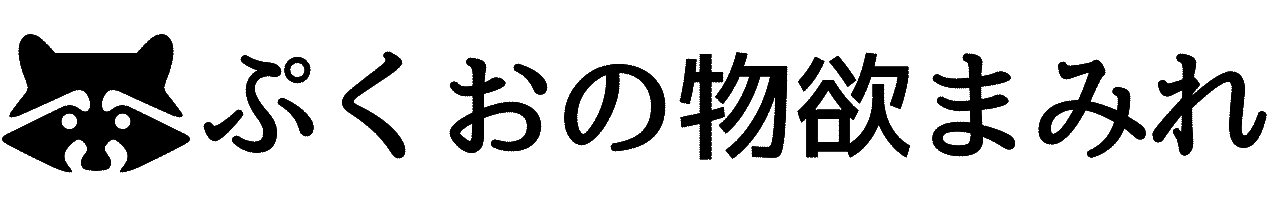













コメントを残す